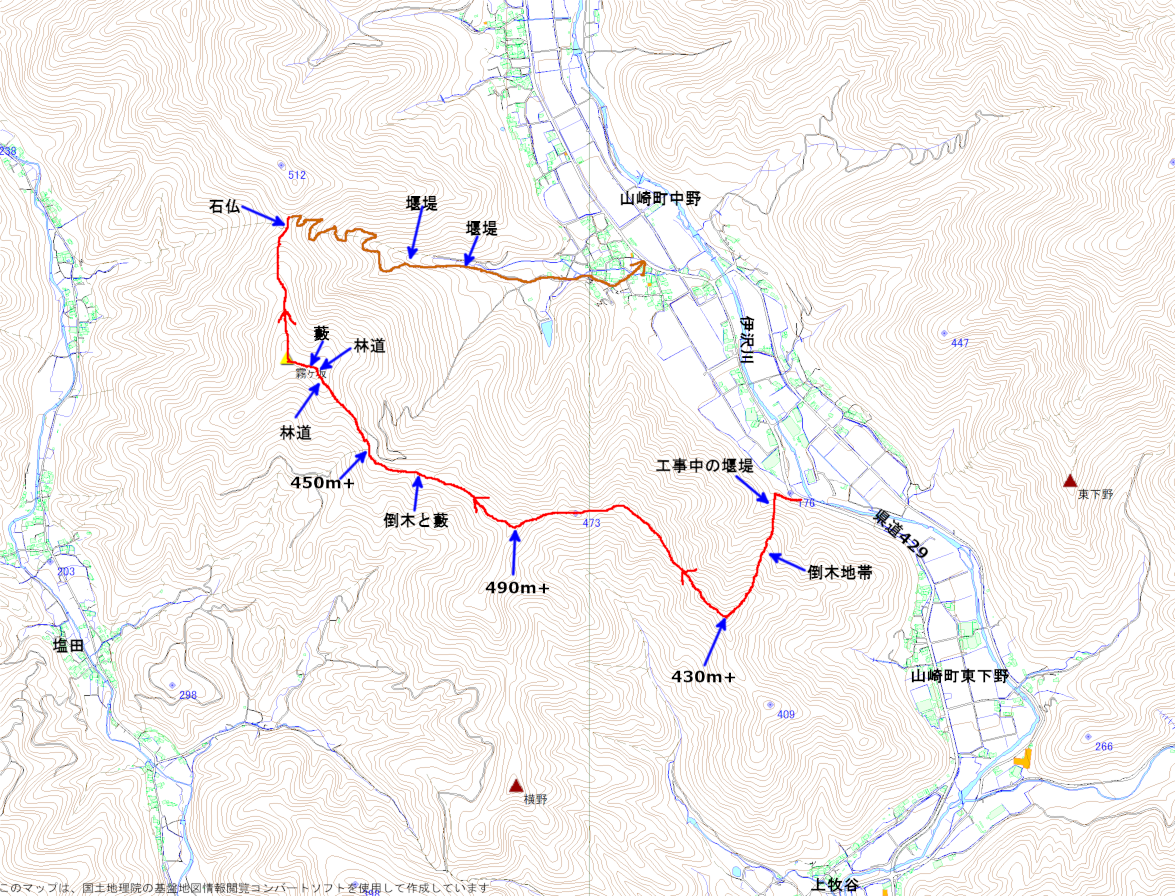2018/04/08に上月の判官三角点に行きましたが、その時と同じように上月の和田の付近から山に入りました。ただし今回は無理やり南の190m+ピークに登らず、人家の脇から谷へ入り、墓地のところから150m+の鞍部に登りました。古い道があります。尾根上も道があり、前回同様に北西に歩きました。ツツジの季節は終わっていましたが新緑がきれいでした。尾根沿いに北に歩き、少し藪っぽい伐採地の南に向きを変えると植林になりました。ここからはしばらく作業道を歩き、植林を登って判官四等三角点(290.07m)に着きました。
さらに西に尾根を歩きましたが、道があるようなないようなところを歩くと道に出ました。この付近は前回と歩いたコースが違います。今回は南寄りに歩いたら道に出たので、少し道を下って大滝神社に行き、その裏から東に登りました。放棄された耕作地がありましたが植林を歩くと道に出ました。少し歩いてから植林を340m+に登りました。前回同様に山頂の道に出て、4基のサイロの脇を降りると舗装道路に出ました。前回はこの道路で戻りましたが、今回は真っ直ぐに歩きました。道があって問題なく歩けます。途中に古い墓地がありました。そのまま道は庄ノ上山に行くのですが、途中で道を間違えて西寄りに行ってしまいました。しかし問題なく斜面を登って道に戻りましたが、2018/02/18に見た石仏は見落としました。山の上には「行者山」という道標があり、その付近だけ岩がたくさんありましたが、何のことだか分かりませんでした。とにかく宇根二等三角点(379.74m)のある庄ノ上山に着きました。周囲は自然林です(写真)。東に庄という集落があり、その上にあるので庄ノ上山なのでしょうか。この付近には「米」とか「姿」とか一文字の地名があります。
庄ノ上山からは道はありませんが北に降りました。笹を避けて降りていくと、地形図の破線道の下に林道がありました。これは2018/02/18に歩いた道です。これを北に歩きました。良い道で新緑を見ながら楽に歩けましたが、355mピークの東付近に来ると太陽光発電施設がありました。これの北を東に歩くと、「上月町杉坂峠森林浴コース」の地図がありました。現在位置が示されていないので困りましたが、ここは2019/06/16に東から来た地点です。峠のお地蔵様がありました。ここから東の植林の林道は2019/06/16に歩いています。その時と同様に326mピークの南から南東に登りました。道はありませんが問題なく登れました。途中で林道に会い、さらに340m+ピークの東では南から林道が上がってきていました。林道の終点は344m地点で、2019/06/16はここまででしたが今回はさらに東に降りました。ちょっと曲がった尾根ですが、あまり急な斜面はなく、落ち葉で滑りやすい以外は問題なく、途中からは里山らしい道も現れました。最後は北に降りて墓地に出ましたが、ここからは降りる道がなく、正解は真っすぐだったらしく、ジグザグに斜面を降りて人家の脇から道路に出られました。
展望 ☆☆☆
藪山度 ★☆☆
地形図は「上月」「佐用」です。